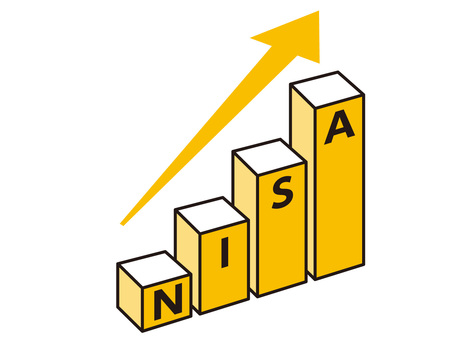
新NISAが2024年から始まるとのことで、YouTubeやXなどでも広告を度々目にします。
投資に関するお得な制度!ではあるらしいのですが、具体的にどんな制度かはわかりません。そこで、今回は何かと話題にのぼるNISAについて調べてみました。
私と同じくNISAについていまいちよくわららないという人も、今回の記事を読んでどんな制度なのかを知ってみてください。
NISAとは? その特徴を紹介
NISA(ニーサ)とは、少額投資非課税制度のことで、投資によって得られた収益が非課税となる制度で、2014年からスタートしました。
2014年からスタートした旧NISAでは、様々な制限がありましたが、2024年から始まる新NISAでは、NISA制度の恒久化、非課税保有期間の無期限化、年間投資上限の拡充が新たに決められ、長期運用がしやすくなりました。
国が貯蓄から投資への流れを加速させたい背景もあって、現在のようにNISAのコマーシャルがテレビやYouTubeなどで頻繁に流れています。
NISAの特徴
NISAには、いくつかの特徴があります。その中でも大きなものとして、次が挙げられます。
- つみたて投資枠と成長投資枠がある
- それぞれ年間投資枠が設定されている
- 非課税保有限度額が設定されている
それぞれを詳しく解説していきましょう。
つみたて投資枠と成長投資枠
新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠によって構成されています。
つみたて投資枠とは、旧制度のつみたてNISAを引き継ぐ枠のことで、購入できるのは信託報酬が低い株式投資信託や国内外の株式・債券等に分散して投資する投資信託などです。
対して、成長投資枠は、つみたて投資枠では対象外の商品も購入することができます。
年間投資枠
NISAには、年間投資枠という、1年で購入できる金額の上限が定められています。
つみたて投資枠では年間120万円まで、成長投資枠では年間240万円まで購入することが可能です。
非課税保有限度額
一見すると、成長投資枠に比べ、つみたて投資枠は制限が多く、利点がないように思えますが、大きな差は非課税保有限度額にあります。
非課税保有限度額とは、NISA口座全体で保有する商品の金額で、成長投資枠なら1,200万円までなのに対して、つみたて投資枠では1,800万円まで保有できます。
非課税枠をより大きく利用できるのがつみたて投資枠のメリットと言えるでしょう。
NISAのメリット

NISAにはいくつかのメリットがあります。どのようなものがあるのか見ていきましょう。
投資で得た収益が非課税
NISA最大のメリットは、取引で得た収益に税金がかからないことです。
特定口座で株式投資などで収益を得たとき、約20%の税金がかかりますが、NISA制度を利用していれば、非課税となり20%の税金を免除できます。
例として、株式投資で10万円の利益を得たとき、通常でしたら20%の2万円が税金として引かれ、手元に残るのは8万円ですが、NISA口座を利用していれば、10万円をそのまま手にすることができます。
このような理由から、NISAはお得な制度として話題に登っているのです。
確定申告が不要
NISA口座内による投資で得た利益は非課税所得です。そのため確定申告をする必要がありません。
確定申告は、普段の生活ではあまり馴染みがないため、投資を始めるにあたって頭を悩ませる問題ですが、その確定申告の手続きを行わなくていいのは、嬉しい部分でしょう。
しかし、課税対象の証券口座を持っている場合は、課税の対象になり、確定申告をしなければならないので注意が必要です。
NISAのデメリット

投資では、どんなものにもメリットと同じくデメリットもあります。NISAも例外ではありません。
NISAのデメリットを把握して、事前にリスクを把握しておきましょう。
1人1口座しか開設できない
NISAで使用するNISA口座(非課税口座)は、1人につき1口座しか解説できません。また利用できる金融機関も1つのみとなります。
金融機関によって取り扱う金融商品はラインナップや、売買にかかる手数料が異なるので、選ぶ際はあらかじめ調べるのがおすすめです。
旧NISAでは、つみたてNISAと一般NISAは併用できませんでしたが、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠で併用することもできます。
金融機関の変更もできますが、1年に1回と制限があり、時間と手間がかかります。
損益通算ができない
複数の投資用口座で取引していて、利益を出した口座と損失を出した口座がある場合、通常の投資では合算して相殺する損益通算ができます。相殺することで、利益を低くして税負担を減らせるのです。
しかしNISA口座で損失が発生し、別の課税口座で利益が発生しても、NISA口座との損失は相殺できません。そのため、課税口座で発生した利益については、全額税金を支払う必要がでてきます。
繰越控除の適用がない
繰越控除とは、金融商品の売却時に損失が出た場合や損益通算ができなかった場合に、その損失を3年間繰り越して利益と相殺する制度です。
通常、確定申告をして繰越控除の適用を受ければ、翌年以降の税負担を軽くすることができます。
しかし、NISAでは利益に対して税金がかからないので、損失分においても税務上なかったものになり、繰越控除の適用を受けることができません。
非課税対象は新規取引分のみ
非課税の対象となるのは、NISA口座で新しく購入した金融商品のみです。そのため、既に持っている課税口座で保有している株式や投資信託などを、後からNISA口座に移すことができません。
まとめ:新NISAで投資を始めよう!
今回は新NISAの特徴とメリット、デメリットについて解説してみました。
NISAは、年間投資枠もあり、「短期間で大きく儲ける」といった投資スタイルには向きませんが、逆に「預貯金のように毎月納める」という長期的な投資スタイルにはピッタリの制度です。
銀行の預金金利が低い今こそ、資産投資を始める時期です。まずはNISA制度を利用して少額から投資を始めてみてはいかがでしょうか。


コメント